機密保持を命ず(2)
「これなんかどう?」
熱い日本茶と芋羊羹をテーブルに並べてからミス・クインシーがリィンに示したのは『劇場版・特捜司法官S‐A』のホーム・エディションだった。
「今日、発売だったの。予約しておいたのよ」
そう言うミス・クインシーは、まるで乙女のような表情をしている。発売日に入手できたことが嬉しくて、一緒に観てくれる人を欲していたのだということがわかる貌だった。
実のところ、リィンはバーリーと一緒に『劇場版・特捜司法官S‐A』を映画館で観ている。男二人で劇場に観に行ったというのは、少々情けないものがあるが、本当に一緒に行きたいジョーカーはこのところずっと音信不通になっている。多分に、解体処分の日を迎えるまで二度とリィンに逢うまいと決めているフシがある――リィンは決してそれを承諾しているわけではないが、ジョーカーが逢おうとしない限り、たとえ特捜司法局に押しかけたところで逢うことはできない。
(ジョーカー……)
ジョーカーと観にいくことができないなら、一人だけでも映画館に出かけるかというと、それも空しい。映画は観たいが、独りでは味気ない。
同じような事情がバーリーにもあるらしく、男二人で観に行くことになってしまったのだ。
(大家さんだったら、なおのこと……かな)
お気に入りの映画を観に行くのに、女性の二人連れというのは珍しくない。けれど単独で来ている女性というのは少なかった、とリィンは劇場の観客を思い出す。一人では、観たくても行きづらいのだろう。
(それにホーム・エディションなら、好きなときに好きなだけ観ることもできるしね)
「それ、つい先日まで劇場で上映さ れてた分ですよね?もうホーム・エ ディションがでたんですか?」
リィンの問いかけにミス・クイン シーの表情が更にゆるむ。
「そうなの。この主演俳優が、いい のよね」
言いながらディスクをデッキにセ ットし
「そういえば……寿退職する特捜司法官がいるっていう噂を聞いたんだけど、六道さん、なにかご存知?刑事さんなんだから、一般に公表されていない情報も持ってたりするんでしょ?」
ミス・クインシーの言葉は、そこで中断した。
立体ディスプレイに「特捜司法官S-A the Movie」の文字が浮かび上がり、劇場版の音楽とナレーションが始まった。
ミス・クインシーは、それ以上言葉を続けることはせずに画面を注視している。
一緒にテレビを見ている時には、途中でスポンサーのCMが入るたびにリィンに話し掛けるミス・クインシーだが、映画には、CMなどないから最後まで息を詰めるようにして観ているのではないか、と想像できる。
リィンの目も画面に向いてはいるが、頭はミス・クインシーの言った「寿退職」について考え始める。
(それって、結婚を機に退職するっていう概念だよね。たしか…二十世紀には、さほど珍しいことでもなかったとかいう……)
特捜司法官にも退職が認められるなら、どんなにか、いいだろう。それは、リィンの望むところでもある。しかしながら、現実問題として、ありえない事だと知っている。
特捜司法官というのは究極かつ最高の合成人間である。
いかに優れた能力を有していようとも、合成人間である以上、彼らに 「人権」はない。
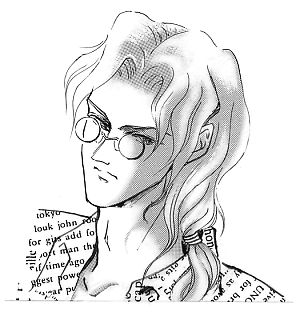 以前、リィンが資料管理室に異動になった際に必死に脳味噌に詰め込んだ「分類総合コード」によれば、完全人間模倣体の合成人間は「人間」の区分に入っている。しかしながら、人権はない。 以前、リィンが資料管理室に異動になった際に必死に脳味噌に詰め込んだ「分類総合コード」によれば、完全人間模倣体の合成人間は「人間」の区分に入っている。しかしながら、人権はない。
特捜司法官は、特捜司法局の職員ではないのだから退職などという概念は当てはまらない。彼らは人としての姿で存在してはいるが、法律的には「人間」ではない。
分類コード上では人間の区分にありながら、法的には人間ではない、という点が矛盾ではないかとリィンは思うが、事実は事実である。
机や椅子といった特捜司法局の備品には、廃棄処分はあっても退職などという項目はない。それと同様のことが特捜司法官についても言える。もっとも、特捜司法官の場合には、能力の劣化を防止するための解体処分になるわけだが。
これは、現在リィンが追っている(ジェンクスがかかわっている)事件においても当てはまることで、合成人間を殺したとて殺人罪にはあたらない。ただ器物損壊罪が適用されるだけだ。
殺人罪にあたらないからこそ、ジェンクスは「この事件の犯人は自分だ」と表明できるのかもしれない。
そのジェンクスは、『特捜司法局から脱走してきた』と言い、同じ口で『特捜司法局の意をうけて動いている』と言う。相反することを言いながら『これまでに嘘をついたことはない』と言う。それでいて恋人でもないリィンを『マイ・ハニー』と呼ぶことを躊躇わない――これは、ジェンクスにとっては、単に嫌がらせなのかもしれないが。
同時に、彼は、自分に協力すればジョーカーの解体処分をなきものにできるとリィンに囁く。特捜司法局の機構そのものを壊すために行動を起こしたのだと主張する。
いったい、どこに真実はあるのか。
ジェンクスの言葉の中に真実はあるのか。
それとも、彼は真実を述べてはいないのか。
嘘をつかないというのは、真実を話すという意味ではない。嘘はつかないが、真実も話さないという場合だってあるのだから。
リィンは、考えれば考えるほど真実から遠ざかっているような気分になる。
顔だけをディスプレイに向けたまま考え事をしていたリィンの横で
「キャー!」
いきなり悲鳴とも歓声ともつかない声があがった。
ミス・クインシーが空になった湯呑をきつく握っている。
リィンが意識を画面にもどすと、そこには主演俳優の秋津がアップで映し出されており、『特捜司法官シリーズ』お約束のシーンになっていた。「犯罪者諸君……」と決め台詞が聞こえる。
(秋津さんのところにも「寿退職」の噂は届いてる…のかな。たぶん届いてる…よね。大家さんの耳にも届くくらいなんだから)
秋津には特捜司法官の友人がいることを六道リィンは知っている。ジョーカーと表裏一体の存在であるS‐Aを大切に思っていると知っている。
(特捜司法官にも人権があればいいのに、退職制度があればいいのに、と秋津さんも願っているだろうけれど)
特捜司法官に「解体処分」以外の途を拓くことができるなら、どのような努力も厭わない。無論、刑事として人間として、犯罪に手を貸すことはできない。それをしてしまったなら、一番大切な人が悲しむとわかっているから。結果的にそれによって新たな途が拓けるとしても悲しませることになるから。だが、犯罪にならないことなら何でもする。秋津も同じ気持ちでいるとリィンは信じている――同じ立場に立つ者として。
* * *
ほぅ、とミス・クインシーが深い息をついた。
画面は、青くなっている。エンディング・ロールまで終了したということだ。
「あの……」
「熱いお茶を淹れましょうか?」
リィンとミス・クインシーが、ほぼ同時に口を開いた。
言いさしてやめてしまったリィンに対してミス・クインシーのほうは、言葉を継いだ。
「あら?六道さん、羊羹たべなかったの?」
情報収集と説明に来たはずのリィンは、寿退職のこと、ジェンクスのこと、そして特捜司法官のことを考えているうちに時間が過ぎてしまい、肝心の時に少し出遅れてしまっていた。映画を見終わった時に、用件をどのようにして切り出すか決めていなかったのだ――単純明快に友人が来ていると言うのか、先にミス・クインシーの情報を引き出すのか、決めていなかったのだ。
「観ることに熱中してたら、食べるの忘れてました」
リィンは苦しい言い訳をする。まさか、芋羊羹は嫌いですなどとは口が裂けても言えない。「芋羊羹いただきます」とミス・クインシーの部屋に来たのだから。
「まあ、まあ、そんなに熱心に観てたのね。ホント素敵ですものねー」
ミス・クインシーは、実に理解できるとばかりに納得し
「だったら、芋羊羹はお持ち帰りになさいね」と手早く包みを用意する。
「あの……大家さん……」
お土産を手渡されるより先に、言うべきことを言わなくてはいけない。
「僕の部屋の居住人員についてなんですけど……」
「増えたの?増えてないの?」
ミス・クインシーは興味津々といった様子で問い返す。
その言葉で、彼女は居住人員について確たる情報をもっていなかったことがわかる。
リィンは一気に虚脱してしまった。
人員が増えた、あるいは、リィンの部屋に誰かいるという情報を持っているわけではないのなら、なにも「芋羊羹」を口実にする必要などなかったのだ。自分のほうから居住人員についての話をしないほうがよかったのだ。
なにしろ、ミス・クインシーは、法より義理人情が好きで、おまけに好奇心を基盤とするおせっかいという悪癖をもっているのだ。リィンのほうから話題にしてしまったなら、彼女の好奇心が満たされるまで解放されないだろう。
「増えてるわけじゃありません……」
リィンは力なく言う。
「ただ、ちょっと友人が泊りがけで来てるだけです」
それを聞くとミス・クインシーは目を輝かせた。
「お友達にも羊羹をもって行ってあげて。それともお饅頭のほうが好みかしら?」
話の方向性が友人についての詮索ではなく、和菓子の方に向かった。
(よかった……)
ミス・クインシーから『友人』について質問されてもリィンには答えようがない。もしも、質問されてしまったなら、何をどう答えても嘘にしかならない。それよりは和菓子が話題になっているほうが、まだしもマシだと思える。結果的に嘘をつくことになっても、罪悪感が薄くてすむ。
「いえ、お気遣いなく……。僕、この芋羊羹だけで充分ですから」
懸命の逃げ口上にも
「だから、六道さんの分は、それでいいとして、お友達の分が必要でしょ?」
ミス・クインシーの頭の中では、友人が来ているからこそいつもより多めに和菓子を必要としている、という図式ができあがっているらしい。
「遠慮なんかしないで、たくさん持って行っていいのよ」
そう言われてもリィンは困る。
「遠慮なんかしてませんって。僕、これで失礼しますから」
なんとかして芋羊羹だけで済ませたい。
(これだけでも消費するのは大変なのに)
リィンの思考は、自分一人で和菓子を消費するという前提のもとに成り立っている。飛騨ジェンクスが、和菓子を食するのかどうかなどリィンは知らない。食べ物の好みなど知らない。というよりも、食べ物の好みがあるのかどうかさえ定かではない。
(これ以上、和菓子の量を増やしたくない)
単に消費するのが困難になるという問題だけではない。
一人分の和菓子なら、ジェンクスにその発生源を問われても、「大家さんに押し付けられた」と答えれば済む。過去にも例があるから不自然なことではない。だが、大量の和菓子を持って帰ったなら『部屋にリィン以外の人間がいるとミス・クインシーは知った』ということがバレるだろう。
それは怖い。怖すぎる。
人ひとりを匿うこともできないのか、と厭味っぽく叱責される場面が目に浮かぶ。仕事柄、機密保持は必須条件なのに、と妙に静かに溜息まじりに言われる声が聞こえるような気がする。
(誰か僕に救いの手を!)
心の叫びに応えてくれる者はいない。
彼の不幸は、まだ終わらない。
|